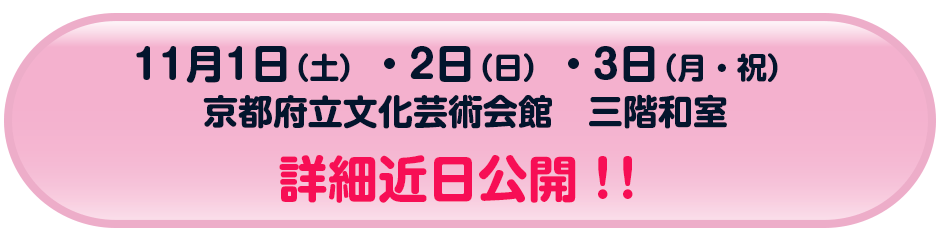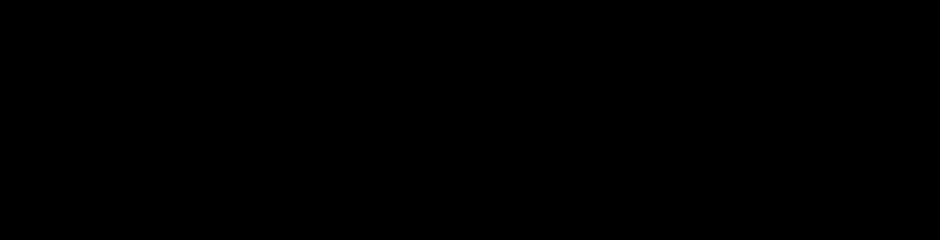今回は、町かどの藝能十周年記念誌に、創設者長田純先生が記載されました文章をご紹介致します。
「おにぎり」や「おむすび」が今日商品になって街中で売られている。
けれど、どれもこれも皆「おにぎり」で「おむすび」ではない。
日本中のそれを食べたわけではないが、商品としてとても「おむすび」は出来ないだろうと思う。
「おむすび」とは『結び』であって、ただ、「にぎっ」てかためたものとは違うのだ。だから「おむすび」は、両掌の中で「くる」っとまわして、「御飯つぶ」がお互いにしっかり「結び」合うように「まわしにぎり」するものなのである。
御飯と御飯がしっかり結びあってはじめて、お米のーー御飯の甘さ、おいしさが生まれてくるのだ。それを、手塩にかけ、食べる人に心を寄せかけてむすぶのである。これではじめて、心づくしの「おむすび」の味が生れてくるのだ。
この「おむすび」にする御飯ーーお米を、藁で炊きあげたら、これこそ今日なら最高の贅沢になるのかもしれぬ。併し、昔は、これが普通だった。
私も四十数年前、毎日藁で炊いた御飯をいただいたことがあるが、今もその味が忘れられない。ほんものの味だからである。
ガスや電気で炊くのは便利に違いないが、それでは「ほんもの」のお米の味は生きて来ない。一度機会があれば、藁炊きの御飯や「おむすび」を召し上がって、ほんとうのお米の味ーーほんものの味を味わっていただきたいと思う。
藁と云えば、鰹の「たたき」も藁火であぶり焼きしないと、ほんとうの「たたき」の味はないという。
藁が身を燃やして、魚の不要な匂いをとってしまうのである。流石、藁はお米の母、身を焼いてまで役に立とうとしてくれる。人はそれを「藁の匂いつけ」というがーー。
「町かどの藝能」は藁であり、藁炊き御飯の「おむすび」である。一つ一つは小さいかもしれぬが、「ほんもの」ばかりである。芯から味わっていただきたい。